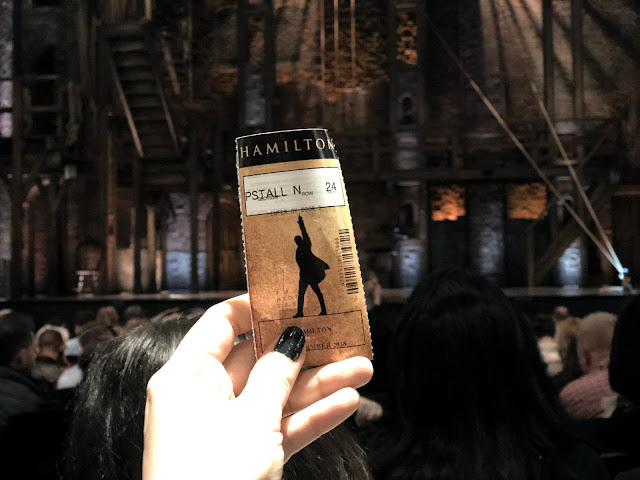演芸、もしくは芸術を目の前にして、その凄さを前に思わず笑てしまう、という経験はあるだろうか。 Dear Evan Hansen をみて息を呑むような瞬間を体験したり、マチルダで反逆的な解放感を味わったことは今も色濃く記憶に残っているが、実はなかなか思わず「笑てしまう」経験はなかった気がする。 ムーランルージュは一曲目のWelcome to the Moulin Rouge! から呆気に取られて声にだしてケラケラと笑ってしまった。隣を見るとパートナーも「うわぁ…な、なんやこれ」という顔をして口を開けて笑みをこぼしている。 昨今のミュージカルは引き算の巧さを競うように出してきた作品が多いように思う。10人満たないキャストで演じ通すDear Evan Hansen, ハモリの美しさを前面にだしてピアノとギターの中心にしたミニマルな演奏のWaitress、時代を代表する傑作と言われるハミルトンもたとえばセットや衣装はモノトーンでとてもシンプルだ。派手な印象が強い芸術、ミュージカルだが、近年は闇雲な派手さよりも、引くところをグッと引く演出こそが巧みである、という共通見解があったような気がする。
そんな時代にMoulin
Rouge! は突き抜けた足し算演出で殴り込んできている。ミュージカルを観たことある人も、ない人も、舞台エンタメ(コンサートなど含む)でおおよそ考えうる演出と効果は全て放り込まれている。 一曲目の曲末にはキラキラの紙吹雪、ド派手でラメだらけの衣装、それに続く舞台で爆発する花火、ワイヤーで天井からでてくるブランコ、紐で吊られるエアリアル、止まっている瞬間が一度もないほど激しく動く振り付け….。 目に飛び込んでくる光と色、アクションの鮮やかさにはエンタメの真髄が詰め込まれている。 驚かされるのは、ここまで「トッピング全部乗せ」なのにこれらが完全にピタリとハマり、整合がとれていることだ。 引き算の演出はその「引き算」の行為自体がテクニックだと思う。しかし足し算そのものはただの浅はかな欲張りだ。それを一流にするには、足し算以上の圧倒的な技術が必要である。 私たちがあんぐり口をあけて、Moulin
Rouge! の前に完敗した気持になるのはもちろんのその華やかな舞台効果に五感を奪われるからではあるが、それ以上に、可能だとは想像しようもなかった完成度のバランスが目の前に展開しているしていることに他ならないからだ。 先述のとおり、ミュージカルには元来派手な印象がある。それはミュージカルはそれまでの古典芸術に比して、あらゆる演芸を呼び込んで組み合わせたことに一つの特徴があり、元来多角的に刺激が展開されるからだと思う。そのため、説明しようとすればするほど、「ミュージカルってそういうもんじゃないの?」という問いを受けそうなのだが、実はオタクとして冷静に頭をひねるとMoulin
Rouge!と比較可能な作品は現代作品に多くない。そう、現代作品とわざわざ断りをいれたのはここがポイントなのだからである。ミュージカルの元来の派手なイメージを築いてきた古典作品たちは華美で豪勢なものが多くあげられる。Chorus
Line、Funny
Girl、 Me and
My Girl、
Cinderellaあたりをはじめ、もう少し現代に近くなると歴史的ロングランを続けているPhantom
of the Opera等があげられるだろうか。このあたりの作風を現代につなぐ形で牽引してきたのがロジャース&ハマースタインやソンドハイム、今も現役のアンドリュー・ロイド・ウェバー卿などである。しかし、これらの作品が初演の幕を開けてからすでに半世紀近くがたっている。当時の「全部盛り」で使われていた舞台効果はすでに古典の域に入っている。レースやフリルでボリュームを出した華やかな衣装はハミルトンやエリザベート等の歴史ものなのなら当然の様に出てくるし、すごい音圧を放つ重厚なアンサンブルもレミゼやウェストサイドストーリーを見に行けば必ず保証されている。舞台の立体的な展開はオペラ座の怪人に行けば拝めるし、プロのダンサーたちによる圧倒されるようなエネルギーを放つ踊りはCatsやChicagoでみることができる。上記は全て「生もの」の講義のステージでは当たり前になってしまった。それぞれの効果を取り上げればそれはむしろ引き算演出の作品でも見受けることができる。
 |
| London のPiccadilly Theatre前 |
しかし、時は50年たっている。圧倒的な「全部盛り」だって革新に革新が重ねられている。現代の本気の「派手派手演出」はそんなものではない。2022年の私たちの派手派手演出のベンチマークはスーパーボールのハーフタイムショーやアイドルのドームツアーだ。Satineの登場シーンの派手派手衣装はブリトニーなみに露出しながら、BeyoncéのDangerously
in Loveのジャケ写を彷彿とさせるキラキラビジューだらけ。照明はマイケルやマドンナのコンサートばりに強いカラー照明をバッキバキにあてる。オペラ座でろうそくが置かれた地下室をみてかっこいい、と思ってた私たちは舞台上で無遠慮にバッチバチに上がる花火をみながら、「あれ、何でいままでこれってやられていなかったんだっけ?」と思っていることに気づく。そう、引き算のかっこいい舞台がセンスよく、お行儀よくシアターに連なっている間に、「全部盛り舞台」は更新されてきていなかった。無意識の中で演出の限界を更新していなかった自分を一瞬にして自覚させられ、見たこともないようなお祭り騒ぎをみせてくれる、それがMoulin
Rougeである。
もう一点、圧倒的に素晴らしかったのが、音楽である。
Moulin Rougeはジュークボックスミュージカルである。オタクの皆様にはおなじみだが、ジュークボックスとは既存の曲を用いて、あとからそれに筋を宛書するミュージカルのジャンルだ。圧倒的に有名なのはMamma Mia、他にはBeautiful (Carol King曲)、Tina (Tina Turner曲)、最新のものだとMJ(Michael Jackson曲)が代表的なものとしてあげられるだろう。正直に告白すると私はJukebox Musicalが苦手だ。そもそも過去観たことがあるのもMamma Miaだけだ。それはJukebox作品の音楽は全く有機的にストーリーとつながってないからだ。製作過程を考えれば当然のことだ。既存の曲から作るため、Jukeboxはシーンや感情、セリフが強く制約を受ける。Mamma Miaも結構突拍子もない話だが、他の作品の多くも、どうしてもシーンが歌と歌を無理やりダラダラと繋げる助走のようになりがちだ。しかし、Moulin RougeはJukeboxとしてその他の作品と大きく違う点が一つある。ここまで読んで気が付くひともいるかもしれないが、ほとんどのJuke Boxは単一歌手/グループのものに縛って劇中歌を決めているものが多い。多くの場合はその歌手へのオマージュや経緯を込めているものなので当然と言っちゃ当然だ。一方Moulin Rougeはあらゆる有名歌手から曲を引用している。それはいわば「平成最強ポップメドレー」なのだ。Whitney Houston、Madonnaにはじまり、Green Day、Britney Spears、Adele、Gagaと連なるセットリストはまさに私が人生の大半を過ごした平成を彩る青春ぶち上げメドレーだった(もちろん70年代くらい曲もあるのだが誤差として許してほしい)。ソロデビューをしたビヨンセが腰と拳を振りながら「かっけー!」と思った中学時代、何度闇落ちしても這い上がってくるブリトニーのToxicやGreen Dayをアホみたいにみんな聞いていた高校時代、エッジを極限まで極めたGaga様が登場を飾った大学時代が曲とともに全身を駆け巡る。最後総立ちで客席中がジャンプと歓声で揺れるカーテンコールはもう10年分くらいの紅白を生でライブ鑑賞してる気分になって、本当に高まった。30年分のあらゆるポップスの名曲を詰め込んだらそれこそ陳腐なxxx歌謡祭ノリにもなりかねないのだが、それをうまくまとめ、本当にシーンごとにぴったりの曲をキュレーションしている音楽チームは圧倒的な手腕を持っていると言わざるを得ない。
そして最後にMR!をすがすがしい鑑後感を成しているのが、「強よ強よガールズパワー」なストーリーの再解釈である。Moulin
Rouge!は言わずとも知れた2001年のヒット映画である。原作映画もまた色々な芸術作品からの引用をしているが、その一つにCyrano
Bergereacというフランスの古典演劇が挙げられる。特にRoxanneという曲はそのまま同作のヒロインを引用している。このCyrano
Bergereac自体も広義のロミジュリ・ジャンルを構成しているといわれ、これ自体がかなわぬ恋ストーリーの翻案(アダプテーション)とされている。つらつらと古典作の名を色々と挙げたが、通底しているのは女性が綺麗な飾りものとして、恋や人生の主体性がほぼ男性にしか与えられていないことが挙げられる。映画Moulin
Rouge!の場合もキャバレーの専属女優のSatineはあくまで花魁のように小屋やパトロンに所有され、終始彼女が「誰のものか」という観点で話は進む。彼女はあくまでか弱く、華美で切ない客体である。ミュージカル版MR!も基本的には映画の大筋のストーリーを踏襲しているのだが、その解釈は大きく異なる。舞台版においては、女性が圧倒的に強く、彼女たちが自らの選択を握りしめ、抑圧の中でもそれを「クソくらえ」を蹴飛ばしていた。例えば、Satineの登場シーン。Diamonds
are a girls best Friend での幕開けは映画と共通しているのだが、そこから続くのはBeyoncéのSingle
Ladies。「私が欲しいならさっさと指輪もってきなさいよ」と挑発するSatineとダンサーたちは、Black
Pantherに扮した2016年のBeyoncé自身のSuperbowlのパフォーマンスさながらだった。
BeyoncéとBruno Mars による2016年のSuperbowl Halftime show
Satineを買おうとする男爵との食事シーンに流れるのも映画のRoxanneから打って変わり、Lady
GagaのBad
RomanceやブリトニーのToxicに合わせて女性たちがバッチバチに息が切れるまで踊る。こんなの恋じゃねぇよ、毒みたいなクソ男と言わんばかりのパフォーマンスが描くSatineや女性たちはもはやただ売られるのを待つ花魁のようなショーガールではなかった。不満には声をあげ、自分の価値はこれよ、と相手の顔面に突き付け、理不尽を蹴飛ばしかねないようなエンパワメントされた女性像がそこにはあった。映画では華美な女性ばかりが舞うダンサーシーンも、すっけすけのストリッパー男性が男女ロール逆転した形で女性とペアを組んでいたり、Lady
Marmaladeを歌うDiva
4人衆も豊満
Moulin Rouge!は今や古くなってしまったミュージカルという芸術形態を、そして陳腐な女性像一気に現代に更新してくれる作品だ。元祖「全部盛り」芸術としてのミュージカルの2020年代の姿を、「こういうことでしょ」とマントを翻すようにいとも鮮やかに演出している。そして、平成を生きた私たちの青春、これからを強よ強よに生きていく私たちの背中をドンと蹴飛ばして、リズムをガンガン刻むBeyoncéのように勇気とともに前に送り出してくれる作品だ。